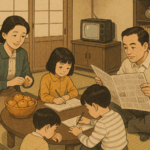「いやらしいことをかんがえると、ちん〇がたつようだ。」
とワイは言った。小学校の、2年生か3年生のころだ。
そしたら、ゆっくんは、はげしくわらった。
ゆっくんは、ワイより二才年上だったから、なんとなくの知識があったのかもしれない。
ゆっくんは背が小さいから、ワイはまったく同い年、なんならゆっくんのほうが年下みたいな感覚でいたけれど、
いま考えれば、二さい年上のぶん、せいしん的にゆっくんはお兄さんだったはずで、
よくかんがえてみると、ワイのことを「こどもやな」とおもっていたようなふしがある。
それで、ゆっくんが、
「じゃあ、ひろくんのちん〇をたたせてみせてよ」
といった。
わいは、
「ええけど、そんなこといわれても、たたんで。」
ゆっくんは、
「いやらしいことかんがえたらたつんじゃろ。そしたら、いやらしいことかんがえれ。」
ということで、チャレンジしてみたが、
「あれ、おかしいな。」
たたなかった。
そしたらゆっくんが、
「わしが絵をかいちゃる」
といって、自由帳に、おんなのはだかの絵をかき始めたのだ。
ゆっくんはめっぽう絵がうまいのだ。
色えんぴつまで使ってかいた。
そうして、ゆっくんは、どんどんと、絵をかいては、ワイに見せるのだった。
「ちょっと、たってきた」
「ワハハハハ!」
われわれは、きゃっきゃいいながら、ひとりの少年のち〇こをたたせようと努力した。
断っておくが、ワイは超ド級の恥ずかしがりやであって
母親にも自分のはだかを見られるのははずかしくて「キャー」といってかくしていたほどである。
だれにもみせたくない、みられたくない、ひみつのパンツの向こう側であった。
しかし、ゆっくんだけは、ちがうのだった。
それこそ、ゆっくんとは、おしりのあなを見ても見られても、なんの感情もわかないぐらいに
不思議に一心同体のように感じていた。
人生であとにもさきにも、あんなに気がねなく、他人のかんじがしないで、なんの警戒もなしに、なかよくいられたのは、ゆっくんだけなのである。
そして、ワイも、絵はそこそこじょうずだったので、ゆっくんと交代で、おんなのはだかの絵をかいてゆき、そのうち、じゆうちょうはおんなのはだかのえでいっぱいになった。
けれど、ワイのちん〇は、そこまでぜんかいにたつまでには至らなかった。
ゆっくんが
「まだまだ、たつじゃろう。もっとたたせようやあ。」
わいも、気持ちでは、もっとしっかりと、たたせたいのだが。
「これいじょう、たたんわあ。この絵じゃあ、いやらしい度がたらんのんじゃろう」
といったら、ゆっくんが、
「そこをなんとかしろっちゃあ。なめてみいさん」
といった。
おさなかったために、よくわからなかったが、ゆっくんがなめろというから、ワイはゆっくんの力作のおんなのはだかの絵をなめてみた。ゆっくんはばくしょうしていた。しかし、たたなかった。
その時、外で、がたんごとんと音がして、母親が、自転車に乗って、帰ってきた。
ワイとゆっくんは、大あわてや。
「かくせ、かくせ。」
そんなワイらのあたふたする様子が、ガラス戸ごしに見えたのであろう、母親は、
「やや!ゆっくんがいる。この子ら、また何かわるいことをしているな!」
と、カンがはたらいたにちがいない。そして、
「なにをかくしよるんかねっ!」
と怒鳴りながら、母親は、どどどどどと、ガサ入れに入る大阪府警のようないきおいで家に入ってきた。
そして、
「みせなさいっ!」
おろおろしているワイの手から自由帳を強奪した。
ワイは、大ごえをあげて泣きだした。
ゆっくんは泥棒ねこのようにそそくさと逃げて帰ってしまった。
母親は、自由帳に何がかかれているかをみとめると、びりびりと引き裂きはじめた。
「なんかね!こんな絵を―!!!だれがかいたんかっ!!!」
そのときの光景は、幼きワイの心象では、仁王立ちした母親が長髪をふり乱し、般若の形相と化して一心不乱にノートを引きちぎりまくり、背後には火炎がごうごうと渦巻いていて、「阿鼻叫喚の地獄絵図」であったと記憶している。
ワイは、ただただ、わんわんなきながら、
「ゆっくんがやった、ゆっくんがかいた、ぼくはかいてない、ぜんぶゆっくんがかいた」
と言いつづけたのだった。
(つづく)